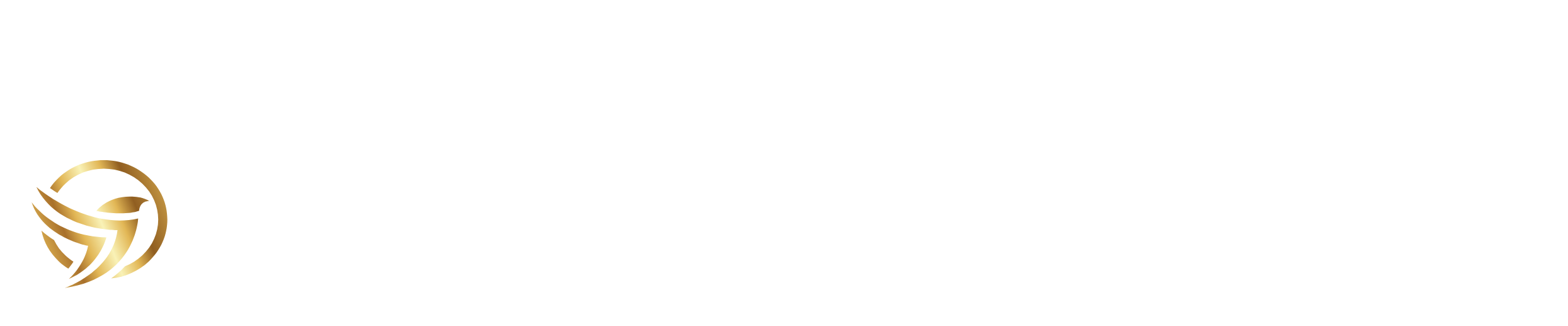目次
初めてのロードバイク選び
こんにちは!管理人のTARAです。
トレーニングや運動不足解消の為に、ロードバイクの購入をお考えですか?
ロードバイクは楽しいですよ!
僕の経験をふまえ、初めてのロードバイク選びのアドバイスをしたいと思います。
おなたにとって運命の一台が見つかると良いですね。
この記事の内容は以下のとおりです。
・車体サイズは一番のポイント!
・自分の用途を明確にする
・フレームの素材について
・コンポーネントのグレード
・それぞれの価格帯について
それでは順に詳しく見ていきましょう。
車体サイズは一番のポイント!

自分にぴったりのロードバイクを選ぶうえで一番大切なポイント。
それはフレームのサイズ選びです。
自分の体に合ったフレームサイズを選ばないと乗っていても体に負担がかかりますし、何よりベストな走行性能が出せないでしょう。
ロードバイクは人間の体がエンジンです。
その人間の体とロードバイクがどれだけシンクロするかが非常に大切なのです。
サイズ選びで大切なポイントは、
①手を伸ばした時のハンドルまでの距離が遠すぎず近すぎない事。ハンドルを持った時に少し腕の角度に余裕があるくらいがベストです。
②シートに座った時のペダルまでの距離が自分の足に合っている。シートの高さ調整で、ペダルまでの距離が軽く膝が曲がるような無理のない状態になる。

上の写真のように、腕にも足にも少し余裕があり、なおかつ窮屈でないポジションで乗れるフレームサイズが適正と言えます。
ただし人の体は手の長さも足の長さもいろいろです。
一番良いのはショップでしっかりとサイズを計測してもらい、適正なフレームサイズを提案してもらうことがベストでしょう。
ちなみにサイズ選びに迷ったら、大きいサイズよりは小さなサイズの方がおすすめです。
何故なら、大きすぎて手や足が遠いサイズはどうにも出来ませんが、小さい分にはシート位置やハンドル位置で調整が可能な場合も多いからです。
もし迷ったら小さい方のサイズを購入すると良いでしょう。
僕は少し小さめのサイズを買いましたが、大正解だったと思っています。
ハンドルやシートの調整に余裕があるのです。
結果、ハンドル高さは少し下げ、シートは大幅に下げて今のポジションに落ち着きました。
もうひとつ大きなフレームサイズだったら、シート調整の方はうまくいかなかったような気がします。
ロードバイクのフレームサイズ選びは「小は大を兼ねる」らしく、大きいサイズより小さいサイズでステムやサドルの位置で調整すればいいと聞いたけど、そうなんだろか?(´・ω・`)
— ぱなっぷ@lapierre乗りになりました(´∇`) (@masa291295) September 12, 2018
それならラピエールのアルチフレームのSサイズも射程に入るんだけどなー#ラピエール#LAPIERRE pic.twitter.com/qAfhe4yahg
ロードバイクのフレームサイズ選びは難しいわね。僕は大体決めたので良いけども、友人が沼にハマって半年以上買えないでいる。
— 33のひと。PBP2019 完走 (@BCNR33_KR4) April 10, 2018
自分の用途を明確にする

ロードバイク選びで忘れたくないのが「何の為に購入するのか?」という点です。
・レースにがんがん出たいのか?
・長距離ツーリングを快適に楽しみたいのか?
・通勤程度で気軽に使いたいのか?
希望する用途によって求められる性能も変わってくるはずです。
自分が求めている性能に届かないロードバイクでは意味がありませんし、希望以上の過剰な性能も必要ないでしょう。
まずは自分がロードバイクをどのように使いたいかを明確にすることが大切です。
もしもレースに出て勝ちを狙っていくのなら、走行性能は妥協しないほうが良いでしょう。
でも長距離ツーリングや通勤に使う目的なら、走行性能よりも快適性の方が大事になってくるかもしれません。
ちなみに僕はロングツーリングが一番の目的でしたので、長距離での快適性とコスパを重視して車体選びをしていました。
まずは自分の目的を決めることから始めると良いですよ♪
フレームの素材について

ロードバイクを選ぶうえで選ばなければならないのが「フレームの素材」です。
大まかに分けると以下のフレーム素材があります。
・カーボン・・・とにかく軽量で疲れにくい。耐久性はやや低い。高価。
・アルミ・・・適度に軽量、耐久性も十分。コスパは◎。
・スチール・・・とにかく丈夫。半面重いのが気になるところ。
それぞれに長所、短所があります。
自分がロードバイクに求めるものによって、選ぶフレーム素材変わってくるでしょう。
簡単に言ってしまえばカーボンフレームはハイコストですが、軽量で乗り心地も抜群です。
アルミは手頃な価格で手に入り、そこそこ軽量で耐久性もあります。
スチールはママチャリなどに使われるほどに耐久性はピカイチ。でも重いのが難点です。
僕はスピードレースに出る目標は無かったので、アルミフレームの比較的軽いものにしました。
カーボンほど高価ではなく手が出しやすかったのも理由のひとつです。
コンポーネントのグレード

ロードバイクにはコンポーネントと言われるパーツがあります。
一般的には「コンポ」と略されることが多いですね。
主にクランクやギヤ、シフトレバー、ブレーキなどの走行に直接関わる部分にあたる部品のことです。
そしてコンポにはグレードが存在します。
日本でトップシェアを誇る「シマノ」を例に見ると以下のようなグレードに分けられています。
・デュラエース(プロ仕様の最上位モデル/22段変速)
・アルテグラ(最上位に近い性能/22段変速)
・105(上位グレード兼価版/22段変速)
・ティアグラ(中間グレード/20段変速)
・ソラ(入門者向け/18段変速)
・クラリス(街乗り向き/16段変速)
・ターニー(ローコストモデル/14段変速)
デュラエースは部品の素材も極限まで良いものが使われ、プロがレースで使うグレードと全く同じです。
その分、価格も高価なコンポとなります。
下位にあたるターニーは、最低限の性能が備えられたローコストモデルとなります。
どのコンポーネントを選ぶかは、ロードバイクに求める性能によるでしょう。
ただし、ローコストモデルを購入してもすぐに上位グレードが欲しくなる方がほとんどです。
最初からある程度のグレードを購入するのをおすすめ致します!
具体的にはソラ以上のグレードなら、レースにもロングツーリングにも順応する性能はあるかと思います。
もちろんローコストモデルが駄目という訳ではありません。
予算や目的と相談しながら選びましょう!
僕のロードバイクは「105」が装備されています。
105を選んだ理由としては、より上位のアルテグラやデュラエースと互換性があったからです。
最上位グレードと同じく22段変速なので、上位グレードに載せかえることがあってもギヤ部分の互換性も高いというわけです。
それぞれの価格帯について

価格は、下は3万円程度のものから上は100万円以上のものまで様々です。
基本的に、
・3万円~5万円の車体は「ルック車」と言われるものが多い。※形だけロードバイクで性能はあまり期待できない
・ロードバイクの基本性能を求めるなら最低10万円くらいのモデルがおすすめ。
・カーボンフレームになると20万円以上が相場になってくる。
以上は覚えておくと良いですね。
とくにルック車と言われる見た目だけロードバイクの「なんちゃって車体」には気をつけましょう!
ネットでもよく販売されていますが、性能は本物のロードバイクに比べてかなり低いものとなっています。
加速、停止、ギヤチェンジ、乗り心地、重量、すべてに関係してくるのです。
街乗りくらいで雰囲気を味わいたいだけなら良いですが、ロードバイクの走行性能を楽しみたいのなら、最低10万円くらいの車体は手に入れておきたいところですね。
また、この先もずっと乗るのか分からないという初心者の方にも10万円くらいの車体はおすすめです。
購入してもすぐに乗らなくなってしまうのでは高い車体を購入しても意味がありません。
また逆に、安いルック車の性能ゆえにロードバイクに乗らなくなってしまうのも残念です。
そう考えると、すぐにレーズに出たりするのでなければ10万円あたりが初心者向けの車体ともいえるでしょう。
もちろん予算に余裕があるのなら、それ以上のグレードを検討してみても良いですね。
初めてのロードバイク選びまとめ

初めてのロードバイク選びについていろいろと説明させて頂きました!
最後に重要なポイントをまとめます。
・サイズ選びは慎重に!できればショップで計測してもらいましょう。
・ロードバイクを購入する目的を決める。
・フレームもさまざま。アルミ、スチールよりもカーボンは高価。
・コンポーネントの内容を知る。「ソラ」以上がおすすめ。105は上位との互換性あり。
・価格は10万円くらいのものがひとまず初心者にはおすすめ
基本的には、どのロードバイクに乗っても問題はありません。
最低限、自転車としては使えるでしょう。
ただ、自分が何を求めてロードバイクを購入するのかが一番大切です。
「自分の目的に合った性能を持つロードバイク」を選べるように慎重に検討してみましょう。
また、ロードバイクの乗り方については是非こちらの記事も参考にしてみてください⇒
いつかあなたとツーリング先でお会い出来るのを楽しみにしています♪